遅刻はそれ程多くはなかったと思います。遅刻3回だったか5回だったかで、欠席扱いか何かになるペナルティがあったように思うのですが、そこは良く覚えていません。
毎日、自転車で、同じような時間帯に、同じような場所を通るようになっていたので、間に合うかどうかをチェックする関門?が幾つかありました。家から高校までは、7.5km程の道のり。父の車で高校の前を通った時に、メーターを見て知っていました。自転車で時速15kmで行けば、約30分です。でも、信号や車の交通量、雨や風その他で、ぴったりとはいきません。
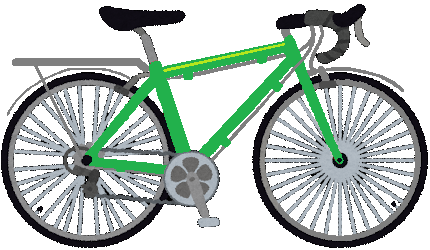
最初のチェックポイントは、家を出る時刻。何時何分くらいなら大丈夫という目安があります。とは言え、雨や風の日だったら、幾分か早く出ないと心配というのはありました。
次に、以前のブログ(tn2.自転車(1)通学でのクラクション)に詳しく書きましたが、後ろから追い抜いてくる車がある時刻帯なら、まず大丈夫。逆に、あるバス停でバスが発車するより遅くなると、間に合うかどうかがやや危ない。他にも、同級生の〇〇君や□□さんを見かけたら多分、大丈夫などがありました。ただ、こうしたチェックには早い遅いがあるので、大まかな目安でしかありません。
それより、腕時計があるのですから、時刻を確認すればよい話なのです。ただ、どうにも「時計の時刻がずれていたら、どうしよう…。」という思いは常にあって、周囲の様子も見て安心するというのがありました。
最後の関門は、校門近くの信号でした。登校時、大きな橋を渡った後、安全の為にも、国道は進行方向の左側を走っていました。しかし、高校の校門は進行方向の右側にあるので、どこかで国道を横断しないといけません。人の習慣というものは、続けている内に、何某かのこだわりができたり、ほんの少しの違いに敏感になったりするようです。登校時刻は、幾らかの余裕を持って出ることが多かったのですが、つい出発が遅くなってしまうこともあります。そんな時はかなり急いで(時に、ゆっくりめの原付バイクを追い抜くこともありました。)行きます。
やがて、このタイミングだとあの赤信号に引っかかると、遅刻になるというのがわかるようになってきます。(決して思い込みではないと思います。)そして校門のすぐ南側に横断歩道があります。高校でも、登校の際、その横断歩道を使うように言われていたのですが、本当にギリギリの時は、そこで信号を待てば遅刻だが、先に少し手前で国道を渡ってしまえば間に合うという状況になることがありました。
時差で動く信号は、(大抵の場合)同じ時刻には同じ色になるというのを、その時初めて知りました。というより、初めて時刻と信号の色をつなげて考えたというのが正しいです。
いざと言うときになったら、その手を使えばいいと思っていたのですが、時折、校門の一つ手前の信号に先生が立って交通指導をしていることがありました。さすがに先生の目の前で、普段言われていることを無視するわけにもいかず、遅刻になったことがあります。本来なら、いざと言うことにならぬ様、早めに出発しろという話なのですが、当時の私は、そんな話はすっかり棚に上げて、内心「あ~、ついてない!」と運の悪さの責任にしていました。
後になって、自分の態度を反省したはずなのですが、未だに反省しきってないのでしょう、自分の抜かりで間に合わせることができなかった信号に、イラッとしてしまうことがあります。反省できてないというより、高校当時のまま成長できてないだけかも知れません。そう言えば、小学校での話だったかな?の交通指導で「赤信号は止まるだけではなくて、急ぐ気持ちも止めてください。」みたいなことを言われましたが、これまた難しいままです。
※ ところで、遅刻したのは、出発時刻が遅くなった時だけではありません。でもその話はまた別の機会にします。